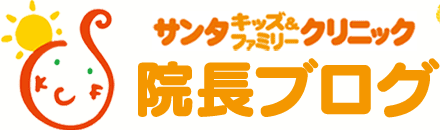投稿者「santa」のアーカイブ
乳児湿疹
赤ちゃんの肌ってどんなイメージですか?
張りがあって
みずみずしくて
スベスベして
きれいな肌をイメージされますよね。
だから、湿疹ができると
とっても心配になります。
アトピーじゃないかって
病院に駆け込むこともあるでしょう。
でも、実は
赤ちゃんの肌はとってもデリケート。
湿疹もできやすいんです。
ですから今回のあわてない育児は
乳児湿疹についてです。
赤ちゃんの肌は、とっても弱くてデリケート。
それは
赤ちゃん肌は、おとなの肌の半分の厚さしかないんです。
皮膚の大事な役目は
外からの刺激から体を守るバリア機能。
実は体は
細菌、ウイルスなどの微生物、大気汚染などの化学物質の
攻撃を受けています。
皮膚は、外敵の侵入を防いでくれているのです。
また
体の内部の水分が
外に蒸発しないようにから守ってくれてます。
赤ちゃんの肌が
水々しくて
スベスベしてるのは、
赤ちゃん自身に水分が多いこと
生まれた時は
お母さんのホルモンの影響で
皮脂の量も維持されてます。
生後3ヶ月を過ぎると
皮脂の分泌量も減り
もともと皮膚自体も薄いので
皮膚のバリア機能がどんどん低下します。
バリア機能の低下すると
体内の水分が外に蒸発して
カサカサしてしまいます。
また
汚れ、ダニ、汗、よだれ、ホコリなどの
刺激を受けて
湿疹がすぐできてしまいます。
赤ちゃんは誰でも皮膚が弱くて、
デリケーだから
湿疹ができやすいのです。
だから
湿疹ができないように
スキンケアーが大切になってきます。
スキンケアーのポイントは二つ。
清潔と保湿。
こまめに汚れを落とすこと。
お風呂で
泡立てた石鹸で、
くびれの部分も丁寧に洗います。
洗った後、石鹸をよく洗い流すこと。
お風呂でもお汗をかくので
芯まで温め過ぎないことも大切です。
そして
お風呂上がりや
汚れを落とした後10分以内に
保湿剤を塗って、保湿をしましょう
毎日根気よく続けると
だんだんしっとりお肌になります。
湿疹が治っても
根本の赤ちゃんの肌は変わらないので
よくなった後も
しっかりスキンケアーを続けましょう。
乳児湿疹を治すコツは
こまめに、根気よくです。
その努力は
10年後のお子さんの肌に現れます。
きっと、感謝されますよ。
明るいこころが病に悩まない日々を生む
人間は全力で生きていくよりも
半分だけ力尽くせばいい。
あとの半分は
自然のめぐみに任せればいい。
弓の矢もそう。
人間はぐっと弓を後ろにひけばいい。
これ以上ひけなくなったら
指を放ち
跡は矢の行く先をみているだけでいい。
毎日の生き方もそう。
できることに力を注ぎ、魂を込め
あとの結果は、元に任せればいい。
日々やるべきことを、やる
なすべきことをなす。
やるべきことをやり抜く生き方こそ
恵ある生き方なんだと思う。
やることはやらずに
人に求めたり
神に頼むのもちがうとおもう。
求める生き方は、やめるべきだと思う。
やるべきことに集中するこことが大事。
朝目が覚めたら
一生懸命働き、汗を流し
やることやったあとの結果は
じっと見つめるだけである。
このように生きる生き方を積み重ねることが
安心の心を生む。
病気の時であっても
生き方は同じ。
やるべきこと、できることをやりきることが
安心のこころを生む
そして
安心の心を生む生き方が
明るい心へとつながり
病気と縁の無い世界へと導いてくれる。
病気と縁のない
明るい心を育てるために
本を読み、色んな方の考えに触れて
自分を見つめ直すことも大事。
そして
成りたい自分に向かって
全集中して生き、働く。
そんな日々を毎日積み重ねれば
病気と縁の無い
明るいこころでいられる。
人間の歯はなぜ32本
人間の歯の数は、
門歯、犬歯、臼歯など
上下16本ずつ32本あります。
他の動物の歯は、
ニホンザルは人間と同じ32本、
猫は30本、犬は42本、象は26本、イノシシ44本と
動物によって、歯の数は様々です。
なぜ人間の歯は32本?
実はどのような歯を持っているかは
その動物の食性をよく表していんです。
例えば
肉食の動物は、
先が鋭く尖った“犬歯”が多く
草食動物は
植物を噛みきるのに適した薄く四角い“門歯”
そしてすりつぶす“臼歯”が発達しています。
何を食べればいいかは、
その歯に当てはめれば
いいというわけです。
人間の歯は
“門歯”が上下2対、“犬歯”が上下1対、“臼歯”が5対
肉を食べるための犬歯 1 : 植物を食べるための門歯と臼歯 7
という割合になります。
これを食事のバランスに当てはめると
動物食 が15%
植物食が 85%(穀類50% 野菜果物35%)
が人間にあったバランスのいい食事ということになります。
ちなみに
こどもの歯は
門歯上下2対、犬歯上下1対 、臼歯上下2対 の計20本
なので
動物食が20%
植物食が80%
成長に必要なたんぱく質を
おとなよりも多めに摂る必要があるんですね。
体の中は、
全て生活に合うようにできています。
その仕組みにあった生き方をすれば
健康で生きていけるんですね
老いは変化ととらえる
老いることを
怖れる人はすくなくありません。
年をかさねれば、
若い頃のような馬力も、体力もなくなり
からだの動きも機敏に動けなかったり
鏡を見れば
肌の衰えや体型も変化していってるのを
感じることでしょう。
人間の宿命として
この世に生まれた限りは
いつかは死を迎えます。
生まれてから、死んでしまうまで
からだは常に変化していくものです。
これは人間だけのことではなくて
この世の全ての物は常に移ろっていくもので
同じ状態でとどまることはないのです。
あと少しで新しい年を迎えます。
新しい年を生きる自分は
今年生きている自分と同じではないのです。
鏡の前で
以前の時と異なる姿を見ると
その事実を素直に受け入れることは
心情的には難しいかもしれませんが
変化に対する受け入れ方には
二通りあると思います。
醜さと取ると受け止めにくくなりますが
必然の変化だととらえたら
その変化に縛られずに
次の段階に進めそうにありませんか?
老いればこそ
わかることもある、伝えることもある
変化を補うために
新たな行動ができるようになるかもしれません。
年を取ることは
次のステージに立つということだと思うのです。
勝海舟からの言葉
勝海舟が以下の様な言葉を紹介します。
「世の人は
首を回すことを知っている。
回して周囲に何があるか
時勢はどうかを見分けることはできる。
だが
もう少し首を上にのばし
前途を見ることを
覚えないといけない」
という言葉を遺しています。
我々は
世の中を見て
今何をすべきかを
直感として見極める力がある。
だけど
その能力は
目先の利益、自分自身の思いだけで
進んでいくと
大きな落とし穴にはまってしまうかもしれない。
下ばかり見ていると
その落とし穴に意外と気づかないもの。
だから
ちょっと首を伸ばして
視線を高くして、遠くをみてみましょう
視線が広がったことで
これから進むべき道が、ゴールへ通じる道が
目の前に広がってくるでしょう。
勝海舟の言葉の様に
自分の進むべき道がはっきりすることでしょう。
これからの迷わず進むために
ちょっと先を見ることが
大事なポイントなのです。
能について
福岡市の警固町に能舞台があると
テレビで紹介されていた。
能楽師さんが作った
能楽堂で
昭和40年に北九州から
福岡市に移転したという。
北九州にあったと言うことに
またびっくり。
その番組の中で
能について説明してくれていた。
能は、見えない世界を舞台に表現していると。
つまり、舞台は室町時代。
そして舞台で演じているのは
鎌倉時代の人。
能面で神や幽霊が乗り移って
喜怒哀楽を表現していると。
そう、人間の、日本人の
ずっと持ち続けている
こころの内面を表に出して
表現している。
能は
世阿弥が完成してから
新作を作ることは認められなかったけど
この能楽堂の能楽師森本氏は
地域の話から4つの新作を発表したと。
そして、能はミュージカルともいっていた。
短いインタビューだったけど
能に触れたくなった。
きっと、日本人としての
こころが揺さぶれる気がした。
下痢
診察中に便のことを聞くことがあります
下痢ですか?
時折
首を傾げながら
答えが返ってこないことがあります。
下痢かどうかって
特に赤ちゃんの便はゆるくて回数も多いので
意外と難しいのかもしれません。
ですから、今日は下痢についてです。
通常便が含んでる水分の状態で表現します。
水分の多い順に
水様便(ほとんど水の状態)
泥状便(泥のような便)
軟便(形がすぐ崩れてしまう柔らかい便)
普通便
硬便
となります。
赤ちゃんの便は通常軟便ですね。
そこで
下痢便かどうかは、
いつもの便と比べて
いつもより
水っぽくて、柔らかいですか?
回数は多いですか?
臭いはどうですか?
血液や粘液が混じってないですか?
などがどうかで下痢かどうかを判断しましょう。
そして便の状態だけでなく
全身状態のよしあしのチェックも大事です。
熱はないですか?
機嫌は悪くないですか?
おしっこの回数はいつもより減ってないですか?
水分をうけつけてますか?
以上のことがある時は
必ず病院をかかりましょう。
下痢や嘔吐を何度もしてぐったりしているようだったら
脱水症が進行してるかもしれません。
便に血が混じり、突然火がついたように泣いたり、泣き止んだりを
繰り返している時は腸重積かもしれません。
夜でも救急病院を受診しましょう。
こどもの下痢は
あまり下痢止めは使いません。
脱水症を防ぐこと
おなか(腸)を休めることが
治療の基本です
下痢の時は
お家での看病がとても大切です。
①水分をしっかり摂りましょう
ジュース(柑橘類はやめましょう)、スープ、
薄めのお味噌汁を
少しづずつ取りましょう
②離乳食を減らしましょう。
下痢の時はおなかを休めることを大事なので
栄養のことは気にしないで
離乳食は中止かまたは半分程度に減らしましょう。
どんな状態のものを食べたら分からない時は
便と同じ状態のもの
水様便なら水のみ
泥状便なら同じようなペースト状
を与えるといいでしょう。
③母乳はOK
④ミルクは、下痢がひどいときは
2,3日は少し薄めて与えましょう。
⑤お風呂は
機嫌もよく、熱もなければ、短時間であればOKです。
特におむつかぶれにならないように
お尻をよく洗ってあげて下さい。
下痢の時は
栄養をあたえないと、水分をあたえないと大変と
あわててしまいますが
家であわてない対応が一番重要です。
診察を受けた時に
どんな生活をしたらいいかを
しっかり聞いていたら安心ですよね
落ち込んだ時にかける言葉
人生は順調な時ばかりではない
つらい時もあるし
悲しみの時もある。
そんな時、心がけていただきたい言葉が
3つあると
欽ちゃんこと萩本欽一さんが
教えてくれた。
その3つとは
「威張らないこと」
「親切にすること」
「いつも以上に気を遣うこと」
と仰っています。
確かに、どんな時にも
この言葉を忘れなければ
きっと運の神様も味方になってくれるだろう。
そして、元気がでて
周りの仲間と喜びと笑顔があふれてくる
と思うのです。
そして、この言葉は
誰よりも
自分が一番つらい時、大変な時、疲れている時に
意識して使う言葉だと思うのです。
愛は元気の源
昨夜は、父の兄弟夫婦が勢ぞろい。
遠路遥々、東京、大阪、宮崎から集まり
久しぶりの再会に
思い出話に花が咲き
池内家のルーツが次々に明かされ
温泉に入るのも忘れるぐらい
楽しく、濃い時間でした
でも楽しい時間は
お決まりのように
あっという間に過ぎていくもの
名残り惜しいけど
次回の再会を約束して
お開きとなりました。
帰る時、
80歳を超えている
おじ、おば、両親の顔を見てびっくり
来られた時より
目が輝き、豊かな笑顔
10歳以上若返ったような
活き活きしたお顔になってる。
そんな両親を見て
ふと思いました。
この生きている時間
“元気でいてもらいたい”と願い
“元気でいてね”と願ってくれてる
思い、思われ
思いが繋がっているから
人は未来に向かって
元気に生きていけるのかも
人は一人では生きていけない
家族の愛
友人の愛
多くの人の愛 に支えられて
生かされている
その愛を大事に受け取り
その愛をまた繋いでいく
それが
元気に生きる源なんだ
不易流行
これは、松尾芭蕉が遺している教えです。
「いつまでも変わらない本知る的なことを
しっかり軸に据え、新しく変化を重ねなさい」
ということです。
要は、流行を追うことを怖れるなと言うことです。
私たちは
生きていく年を重ねていくと
若い時に比べて
体力が衰えたとことに気がつく人も多くなるし
なかなか眠れなくなったと
嘆かれる人も多くなります。
そんな時、よく口にされるのは
「若い時に比べて・・・・」とか
「若い人について行けない・・・」など
日進月歩で変化する世の中の流れに
ついて行けなくなったと自覚してしまい
なんだか元気が削がれてしまうことが
あることも増えてくるでしょう。
年をとると
時代の流れについて行けないと
諦めてしまい
どこか孤独やさみしさを感じてしまうことも
多くなることでしょう。
最後まで
活き活き生きた松尾芭蕉が諭してくれているのです。
可能な限り流行を尊重し
流行を人生に取り入れると
日々の暮らしに色がつき
さみしさなどが遠ざかり
明るく元気になるのではないのでしょうか。