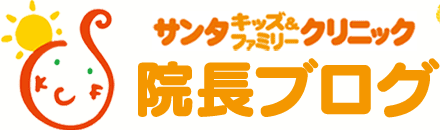投稿者「santa」のアーカイブ
人の死亡率は100%
人間には寿命があります。
どんなに健康に気をつかい、
最新の医療を受けたとしても
いつかは死んでしまいます。
これは
避けることのできない運命です。
今日本の平均寿命は80歳程度ですから、
現在の年齢で平均寿命を考慮して
自分はこれから何歳ぐらい
生きれるのか?生きたいのか?
が考えることができます。
そして
それを目標に
今から10年をどう生きるのか?
20年後はどうなっていたいのかという
ビジョンを立ててみると、
生きていく目標がはっきりしてくるでしょう。
100歳まで生きようとすれば
大変な努力が必要です。
でも50歳まで、60歳まで、70歳まで
健康に生きるためにはどうしたらいいかを
10年刻みで考えれば、
具体的なイメージもできやすいでしょう。
すると
意外と時間の流れの速さも感じるかもしれません。
すると、一日一日が貴重に思え、
大事に過ごせるでしょう。
そして
目標まで十分満足して生きることができれば、
その先は、これだけ頑張ったからと
後は自由に生きるという決断もできます。
残りの人生をいかに充実させるという、
クオリティ・オブ・ライフを考えていくという
人生の選択もできます。
そして誰でも最後の時を迎えます。
でも最後を自分ひとりで決めることはできません。
元気でぽっくり逝きたいと思っても、
現代医学では
死なせてもらえず、
寝たきりや長い長いリハビリ生活を
余儀なくされることもあります。
長生きをすれば認知症の問題もあります。
どう生きていくのか?を考えると同時に
どう死ぬのかも考えていく必要があります。
それには、年齢、性別、環境、性格、
そして
人生観や死生観といった要素が全て絡み合っています。
あなたと同じ人生を歩む人はひとりもありません。
あなたの生き方に悔いが残らないように、
どうやって生涯を終えたいのかを
考えて生きてくことも、
どう生きるのかと同じように大事だと思います。
☆お盆期間中も
通常通り診療します。
知足
知足という言葉があります。
この言葉は老子の
「足るを知る者は富み
強めて行う者は志有り」
という言葉に由来していると
言われています。
仏教には
これとにた言葉で
「知足安分」があります。
この知足を
老子の言葉を辿ってみると
「人間の真の富み、
つまり豊かさとは
精神の自由と簡素な生活の中にある。
自分の能力をわきまえ、
地位や財産を高望みしない。
己に見合った
こころの充足した生き方に努めよう」
と言っているのです。
物に縛られず
こころが自由に生きていくことが
大事だと教えてくれているのでしょう。
☆お盆期間中も
通常通り診療します。
医戒
かつて大阪で適塾という
医学を教え、広めた私塾が
緒方洪庵によって開かれ
当時では最先端であった医学技術を
駆使して
多くの命を救っただけでなく
その後に日本の発展に貢献したことは
現代でも多くの人が知っています。
緒方洪庵の素晴らしさは
それだけでも
充分伝わってきますが
緒方洪庵の遺した遺訓に
次のような言葉を遺しています。
医者として生きる僕にも
忘れてはいけない言葉ですので
ここに記しておこうと思います。
「医の世に生活するは人のためのみ、
人の患苦を寛解するの外、
他事にあるものに非ず」
「ただ病者をみるべし。
長者一握の黄金を以て
貧士隻眼の感涙に比するに
その心を得るところ如何ぞや。
深くこれを思うべし」
医師の僕が
大事にしたい言葉との出会いです。
☆お盆期間中も
通常通り診療します。
汝は12時に使われ、老僧は12時を使い得たり
これは超州禅師が遺した言葉です。
この言葉の意味は
時間に使われるな。
自分が主人公になって
時間を使いなさいという言葉です。
何が起こっても、何があっても
自分が主人公になって生きなさいということ。
例えば
物事がうまく進まない時
人は壁にぶつかったと感じます。
その時、どうしますか?
壁を乗り越えるために
自分のモチベーションを高め
乗り越えようとしますか?
それとも
壁の前で
座り込んでしまい
ただ、目の前の壁があることに
嘆き悲しむことしかしませんか?
どうしますか?
どちらも、あなたの人生。
壁があなたの人生を決めるわけではなく
あなたが主人公になって
その壁にどう立ち向かうのか?
一事が万事にこれはあたります。
あなたは人生劇場の主人公です。
壁も、時間だってあなたの意志で使い切りましょう。
☆お盆期間中も
通常通り診療します。
叱り方
病院でも走りまわってるおこさんの
お母さんに、
”叱るってどうしたらいいのでしょう”と
きかれることがあります。
今は
叱るよりもほめて育てることが
推奨される時代。
だから、
中々叱ることができない
お母さんが増えているのも事実です。
1歳半を過ぎると
こどもを様々な危険から
防いであげないといけません。
だから
叱らないといけない場面は
度々起こります。
ですから
今回は、叱り方について。
ポイントが3つあります
絶対叱ってもらいたいのは
①命に危険がある場合。
その時
「こら!」「だめ!」「めっ!」と
大きな声で言います。
これは、危険に面してるので
自然に大きな声が出るかもしれません。
ただ
これを使うのは1回だけ。
何回も使ってると
段々声が大きくなって
感情的になって
思わず手が出てしまうってことにも
なりかねません。
感情的になったり
体罰をしてしまうのは
どんなことがあっても
してはいけません。
次に
②こどもに責任をとらせるしかり方
例えば
おこさんが散らかして遊んだときは
そんなに散らかして、お片付けしなさい」と
注意するのは大切です。
でも、
こどもだけでは、お片付けできないかもしれません。
ですから
叱った後
ほっとくのではなく
お片付けするまで
側でそっとみてあげて
困っいたら
”一緒に片付けようね”と
やさしく助け舟を出してあげることが
叱り方と同じように
大事な事でしょうね。
一回叱ってもわかってもらえず
何度も繰り返し言わないといけないことって
以外と多いもの。
最後は
③継続的に使うしかり方
1回目は「やめなさい」
2回目は「さっきもやめなさい」っていったでしょう
3回目は「ちょっと、おいで」と言ったり
あるいはお母さんがこどものそばに行って
両手をおこさんの腕に置き、静かに
「ママはやめなさいといいました。」と
おこさんの目をみて
それだけを言って、その場を去りましょう。
それで十分効果があります。
叱るのと同様な言葉で”怒る”という
言葉があります。
この二つの言葉の違いは
愛情があるかどうかです。
愛があれば
その子のことを大切に思えば
その子のためを思えば
どんな叱りかたでも
必ずこどもに伝わるものです。
ですから
自信を持って
おこさんに愛情をもって
真正面から
対峙することが大事なんです。
☆お盆期間中も
通常通り診療します。
違和感を大事に
人間は
起きている時
頭をフル活用して
様々なことを考えている。
それは
情報が頭に入ってくるからだけではなく
目に見えてきたこと
耳に聞こえてきたこと
味も、匂いの情報も
感じたらそれが自分にとって
どんな意味があるかを瞬時に意識しなくても
考えて、様々なことを判断していく。
だから
日々、いろんな不安や疑問が
頭の中に湧き上がり、渦巻いてくるでしょう。
これは生きている限り続き
この行為が生きていることだとも
思えるのです。
そして
生まれた疑問や不安をそのままにせず
その不安や疑問を解決しようと
行動しだすでしょう。
行動するために考え、考え抜き
ひとつの解決策が生まれることでしょう。
この解決策は
アイデアとも言えるし
このアイデアがあったから
人類は進歩してきたのです。
これは人類の進歩だけでなく
ひとりひとりの進歩、進化につながるのです。
ですから
今感じている疑問、不安を
大事に生きていくことが大事だと思うのです。
☆お盆期間中も
通常通り診療します。
生活道⑤ : 手紙を書く】
手紙を最近は書く機会が
少なくなりました。
電話やメールやラインなど
色んな伝達手段が増えました。
これらは
あっという間に
自分が伝えたい時に
相手に伝えることができます。
だから
書くのにも、相手に届くのにも
時間がかかってしまう手書きの手紙は
スピード感ある
現代社会では、億劫がられるのも
わかる気がします。
でも
こんな時代だから
手紙を書くことが大事だと思います。
丸山敏雄先生は
とても筆まめで
心血を注いで手紙を書いた
言われています。
手紙は
お互いの会話だから
気がついたら
すぐに書きなさい。
受け取ったなら
すぐ返事を書かないと
会話としての
手紙の意味をなさなくなると
おっしゃって
とても手紙というものを
大事にされました。
そして
手紙の書き方として
①わかりやすく
読みやすい文字で、簡単に、明確に
②礼儀正しく
心を込めて、相手の立場になって
③早く、美しく書く
事が良いと言われています。
最近では
手紙を受け取ることが少なくなりましたが
その手紙を受け取ると
その方の字をみると
その人の
姿が目に浮かんできませんか?
そして
その文面に
その人の生の言葉として
思いが胸に飛び込んできませんか?
手書きの字をみると
その人の思いが
ひしひしと伝わってきませんか?
そして
温かい気持ちに溢れてきませんか?
それは
メールやラインなど
デジタルの文字では
感じられないものではないでしょうか。
手紙は
直接話すよりも
心に響くことがあります。
会話は
言葉としての音は消え
後には残りません。
でも
心のこもった手紙の文章は
形として
いつまでも手元に残り
必要な時にくりかえし
人を励まし、力を与えてくれます。
心を込めた手紙
手紙を書く気持ちを持って
生きていくと
きっと
いい人間関係が生まれるのでは
ないでしょうか?
からだの音
からだの中には音がある。
心音や呼吸音、お腹の動く音
僕たちはその音を聞いて
患者さんの状態を判断します。
でも
実際にはからだが発して音は
もっと、もっとある。
血管に血液が流れる音だって
川の流れのように
血液が太い血管を流れる時や
細い血管を流れる時には
まるで大河や小川を流れる時の
音のように。
そしていつも同じところでも
閑かに流れる時も
荒れ狂ったような時もある。
他にも
細胞同士だって
信号を出し合って連絡している。
からだの中には
聴診器ででは判別できない音に
あふれている。
その耳に聞こえない
音なき音を聞き分けるのも
僕の臨床医としての仕事。
からだの内なる音、声を聞き
そしてその声を患者さんに伝えるのが
僕の医師としての仕事です。
自粛警察に学ぶ
コロナ流行時には
3密に気をつけようと
ひとりひとりが気をつけていましたが
どうしても、羽目をまずしてしまったり
自分本位の行動をとってしまい
感染を広げてしまうということがありました。
その様なことを防ごうと
ひとりひとりが気をつけるだけでなく
自分の周りに
3密を守らない人がいたら
その人を積極的に取り締まりならぬ
注意して回ろうという
行動を起こす方が多くいらっしゃいました。
そのことを”自粛警察”と呼んでいました。
今はコロナ終息と共に
自粛警察という言葉自体も
死語になってしまいましたが
これに似た言葉に
”健康警察”ということがあるのでは?
と思うようになりました。
健康警察
少しでも健康から外れると許せなくなってしまう。
健康であるためにこころを砕き
からだにいいと言われる情報を集めることに
神経を使い
自分の健康を状態を
常にチェックしないと落ち着かない
健康警察。
健康警察は
自分自身に対してなので
自分以外に対しての実害は
少ないかもしれませんが
自分自身をどんどん苦しめていってしまいます。
健康警察を続けていると
五感で満足するよりも
これが健康にいいと信じることに
安心を感じるようになってしまいます。
でも人は最後は
死んでしまうし、その前に
病気になってしまうことがほとんどです。
熱心過ぎるほどの健康警察で
その時に
健康のためだけに生きていなければいいかな?
と思ってしまいます。
健康警察もほどほどで
納得のいく人生を歩んで欲しいと思います。
無償の愛とは、こどもから親に捧げるものだ
この言葉をきいて
多くの人はあれ?本当?と思ってしまうと思います。
普通は、親の愛が
無償の愛なのでは?と思われた方も多いでしょう。
この言葉は
マイケルジャクソンが
2001年3月にオックスフォード大学で
「こどもと親」について
スピーチをした時の列記とした
講演からの言葉です。
そう聞くと
やっぱりマイケルジャクソンって
変わってる人
通常の人とは感覚が異なる人
だったんだ思いますが
この言葉の真意を知ると
納得するので
今日は紹介しようと思います。
マイケルジャクソンは
このスピーチで
「親との間にどんなことがあったとしても
どうか親を赦してほしい。
親を赦して、親に今一度
愛するとはどういうことかを
教えてあげて欲しい。
親にひどい目に合わされたと思っている人も
親に手を差し伸べてほしい。
あなたたちにお願いすると同時に
わたし自身にも願う
私たちの親に、無償の愛をを
届けられるようにと。
こどもに無償の愛をとどけられてこそ
親はどうやって人を愛したらいいのか
学び直せるのだから」と
語られました。
ここまで聞くと
幼児期親から虐待をうけてたらしい
マイケルジャクソンだから
出てくる言葉かもしれませんし、
現代では親がこどもに手を出してしまう
報道も多く
そうしたこどもたちにも届く
メッセージだとも思います。
でも、よく考えてみると
僕たちは
親になっても、ならなくても
最初はだれかのこどもだったのです。
自分がどんな育てられたとしても
自分が満足に生きていなかったとしても
自分の親を赦し、愛することを
しないと
自分のこどもにも愛を届けることができないのです。
最近、親ガチャという言葉が生まれました。
親は選べないから
どんな親、自分が望まない親だとしても
親に無償の愛を届けられて初めて
こどもだけでなく、家族も友人も
周りの人全てを
愛せるようになるのかもしれません。
こどもを愛すると同時に
まずは自分の親を愛しましょう。