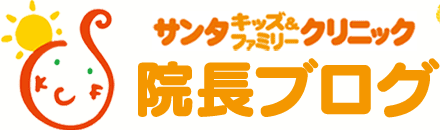「今日の言葉」カテゴリーアーカイブ
無事、是、貴人
この言葉は中国唐時代の禅僧で
臨済宗開祖となった臨済義玄の言葉です。
無事とは
世間一般でいう平穏無事の無事とは違い
外に向かって探し求めるこころがなくなった
ところを無事という。
努めて無事に徹すれば
そのまま仏と変わらない人
則ち貴人であるとするという意味のことなのです。
貴人とは
悟りを得た気高い人のことである。
ちなみに貴人はきにんと読む。
禅宗で目指すところの悟りは
こころの平穏、安心にあるということです。
恩
日本人には
昔から恩を重んじるところがある。
恩を忘れてはいけない。
恩は返さないといけない。
という気持ちは恩を受けると
自然と湧いてくる気持ちです。
アメリカの文化人類学者ルース・ベネディクトが
第二次世界大戦中、アメリカの敵国である
日本を知るために書かれた
名著書「菊と刀」は
恩の本来の意味は負い目であり
恩を忘れないことが
戦前の日本人のなかで最高の価値観であると
書かれているのです。
かつて、日本人にとって
恩は負債で有るから
返さないといけないものだと考え
受けた恩は返すと
親孝行などを大切にしてきたのだと思います。
現代は
もらった恩も意識しないと
忘れることが多くなってきてる気がします。
もらった恩は
返さないといけないという
日本人の美学を忘れずに
生きていかないといけないと思うのです。
人にはどれほどの土地がいるのか
人にはどれほどの土地がいるのか
という短編小説を
トルストイがロシアの民謡をもとに書いています。
広い土地を欲しがっていた農民が
土地をもつ老人と交渉し
長老から
一日歩いただけの土地を与えよう
但し、日没までに
ここに戻ってこないとおまえの負けだといわれ
農夫一日中必死に飲み食いも最小限におさえ
早朝から歩き回った。
そして日没寸前間一髪のタイミングで
帰ってきたのだけれど
農夫は疲労と空腹の結果
着いた途端ばったり倒れて
そのまま死んでしまったのです。
農夫は穴を掘って
そこに埋葬されたのです。
結局最終的にその農夫に必要だった土地は
埋葬分の土地だったのです。
この話を読んで
あなたは何を感じますか?
夫婦円満の極意
人が常に守るべき5つの道徳
「仁義礼智信」を儒教では
「5常」といって大切にしていることです。
そのうち孔子は「仁」すなわち
「人を思いやる」ことを最高の徳としました。
仁とは思いやりの心で
他人を愛し、利己的な欲望を抑えて
行動することです。
つまり
自分が立ちたいと思えば
他人を立たせ
自分が達成したいことがあれば
他人の達成に力を尽くす。
仏教でいえば
「利他のこころ」と言えます。
この孔子が優れた人の条件として
あげているこの言葉こそ
自分以外の人とコミュニケーションをとる
大切なことを伝えていると思います。
自分の一番身近な他人といえば
夫婦であり、親子で有り
その場合にも忘れてはいけない
こころのあり方と思うのです。
人の弱さこそが、人を強くする
人は必ず老いてきます。
病気になることもあります。
老いてきたり、病気になると
自分でできることは
どうしても限られてきます。
限られることと言えば
この世を去る直前や
死が迫ってくると
何もできなくなってしまうと思うけど
死が迫ったときに
患者さんは大きな力を発揮すると
聞いたことがあります。
死が間近に迫ると
様々な後悔や苦しみも中で
初めて自分の弱さに気づき、受け入れ
みんなに感謝して
この世を去って行くのです。
死ぬ間際でなく
少しでも元気なうちに
自分の弱さを認め
感謝して生きることができるとしたら
より後悔の少ない人生を送ることが
できるような気がします。
どんな風に最後を迎えても
どんなに人は弱くなっても
できることがあるのです。
小善は大悪に似たり、大膳は非情に似たり
この言葉の意味は
小さな善行は
相手を思いやったことであっても
結果としてその人をダメにする
可能性だってある。
それに対して
本当に相手のことを
こころから思うのであれば
厳しい言葉や叱責で
非情とおもわれような教育が必要な時もある。
相手のことを思えば思うほど
厳しくすることがあることがあるのに
今の世の中は
厳しさだけの行為だけがクローズアップされて
その行為の深い意味が
わからなくなってきていることために
教育者が萎縮している現状にある今。
今後、こどもたちが
どのように成長していくのか
ちょっと心配になるのです。
断捨離の本質
「断捨離」という言葉は
2010年の流行語大賞にノミネートされ
多くの人々の心に響き
生き方に影響した言葉でしょう。
この言葉がどうして生まれたかというと
この言葉の提唱者やましたひでこ氏は
当時世界中に広がっていた
「もったいない」という固定概念に凝り固まった
こころにヨガで言われたことを取り入れ
より具体的にしたものいうのです。
ヨガには断行・捨行・離行という
考え方を取り入れたのです。
「断」は入ってくる要らないものを断つこと
「捨」は家にある要らないものを捨てる
「離」モノへの執着から離れること。
この意味を聞くと
断捨離を実行するために
何をすべきなのか、目的と共に
具体的になりませんか?
不要なモノを断ち、捨てることで
モノへの執着から離れ
身軽になって、縛られることのない
快適な生活と人生を手に入れようという
言葉なのだと
理解できますよね。
「もったいない」という言葉は
日本人ならではの
モノを大切にする言葉だけど
そこにこだわると
捨てられない、モノにあふれることになる。
そこで
「断捨離」という言葉が出てきたのも
自然の流れかもしれません。
「起きて半畳、寝て一畳」の続き
起きて半畳、寝て一畳という
言葉があります。
これは
人間生きていくためには
起きて半畳、寝て一畳のスペースが
あればいい。
別に広い家に住まなくても
いいのだよ
という言葉です。
実はこの言葉には続きがあって
「天下をとっても二合半」と続くのです。
天下をとったとしても
一食に二合半以上のお米を食べきれない
というのです。
ここまで読むと
このことわざのいいたいことが
ぐっと明らかになってきます。
必要以上に欲しがって
手に入れても
使いきれるものではない。
人間が生きていくのに必要なものって
意外と少ないものなんです。
ものにあふれる現代に生きている
自分たちにこそ
必要な言葉なのだと思います。
親子は一世、夫婦は二世
親子は一世、夫婦は二世
ということわざがあります。
親子は一世とは
親子の関係は現世(この世)だけで終わる
一世のものだということ。
夫婦に二世の二世とは
現世と来世を合わせて二世のいみである。
夫婦になると
来世まで末永く連れ添うことであり
愛情や信頼で結ばれた夫婦の方が
血縁である親子より結びつきが強い
ということを示した言葉です。
人民の人民による人民のための政治
これはアメリカ合衆国第十六代大統領
エイブラハム・リンカーンの有名な言葉ですが
リンカーンは、その他にも
「最終的に大切なのは生きた年月ではなく
その年月ではなく
その年月にどれだけ充実した生があったか」
という言葉を残している。
人生はいつ終わりの日を迎えるか
どんな風な終わり方になるかも
本人はもちろん
誰にもわからない。
だから長生きを目的にせず
今を充実して生きることが
大事なのかもしれない。
またアメリカの建国の父ともいわれている
ベンジャミン・フランクリンは
「長い人生がよい人生だとは限らない。
しかし、よい人生は充分に長い」
という言葉を残している。
どう、今、この瞬間を生きていくかが
良い人生を送れるかどうかの
ヒントになることを教えてくれているのです。
☆本日まで休診になります。
急な病気などの場合、防府市休日診療所、山口こども急病センターなど
救急病院を受診ください。