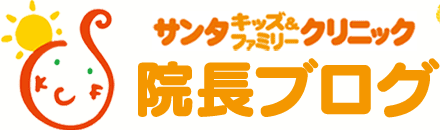「今日の言葉」カテゴリーアーカイブ
やさしく生きる
「自分に厳しく、相手にはやさしく
という自己を確立しなさい」
これは
司馬遼太郎が小学生向けて書いた
「21世紀に生きる君たちへ」の中の言葉です。
司馬遼太郎氏だけでなく
僕たちも
こどもたちに向けて
人にに優しくしなさいなんて
言うことはよくあります。
でも、優しくするって
人間の本能ではないので
やさしさを身につけていけないものなので
訓練して身につけていけない。
だから口を酸っぱくして
言ってしまうのだろう。
やさしさを身につける訓練って?
いつも他人の傷みを感じ
労りの感情をもつことで
やさしさは育つものだと思う。
でも
他人のこころの傷みを感じることって
限られた個人の経験だけでは
意外に難しい。
自分の苦しい傷みを経験した時には
他の人にもらったやさしさを
いつも忘れないようにすること
そして
読書や他の人のつらい話しを聞いた時に
我がごとと感じる感性を育むことが
必要だと思うのです。
他人のことを思えあえる
やさしさにあふれる世界の実現になるヒントが
この言葉にあると思うのです。
しあわせになる道は
心理学者のアドラーが
「自分だけでなく、
仲間の利益を大切にすること。
受け取るよりも多く
相手に与えること。
それが
幸福になる唯一の道である」と
言っています。
人はひとりでは生きていないし
ひとりだけで生きていることも
できません。
どんなに才能があふれる人でも
誰かの支えがあってこそ
生きていけるのです。
自分がしあわせになるためには
周りの人たちがしあわせであるのが
絶対条件なのだと思うのです。
ボランティア
ボランティアというと
何かを見返りを求めないで
してあげることって
思うだろうけど
僕は
ボランティアは、何かをさせてもらうことで
学ばさせてもらっている。
だからそれ以上の対価を求めないというのが
ボランティア活動を重んじるアメリカ人の
考え方です。
つまり
僕たちは
ボランティアをしたということに
満足して終わることが多い気がする。
でも、させてもらったという
意識を持って行うと
その謙虚な気持ちが
深い人間形成に繋がるのだと思う。
ソプラノ歌手の佐藤しのぶさんは
貧しいこども達に勇気を与えるために
度々海外に行かれたようですが
歌った後に
集まったこどもたちに逆に励まされ
世界には理不尽にも極貧のこどもたちの
いることを知り
その貧しさを解決できない自分の無力さを
感じたという
感想を遺されています。
ここに
ボランティアをする
本当のこころがあると思うのです。
継続は力なり
世の中には、頭がよくて
自分よりも優れた人は一杯います。
そんな中で
たくましく生き抜くためには
どんなつまらないことでも
どんな小さいことでも
きちんと最後までやり抜くこと。
そんな小さいことでも
継続して続けると
「これをさせたらこの人の右にでる者はいない」
そう言われるまで
決めたことをコツコツやり抜いていく。
これは
昔から言われている
成功の秘訣。
天職
神学者、哲学者そしてオルガニストでもあった
シュバイツァーは
30代になって突然
アフリカに行くことを決意しました。
それまですでに
哲学者そして芸術家として多忙の生活を
送っていたにもかかわらず
アフリカの人を助けるための
医学の勉強を始めたのでしょう。
30代になって
しっかりした職業があるのに
どうしてまた医学の勉強をしようと
考えたりするのか?と
周りの人はびっくりして
シュバイツァーの決意を止めようと
説得にかかったのですが
オルガンのビルド先生は
「神さまが呼んでいるらしい。
神さまが呼んでいるというのに
わたしは何をすることができようか」
といって
シュバイツァーのアフリカ行きを
応援したそうです。
仕事のことを
ドイツ語ではberufといって
神に呼び出されるという意味らしいです。
日本では天職と言いますが
今やっている仕事は
神さまから呼び出された者なのです。
キーシンのピアノコンサート
キーシンはロシアのピアニストで
幼少時から大天才ピアニストとしてデビューして
デビュー以来
ずっと第一線で活躍している
ピアニスト。
現代は一流ピアニストに
なるためには
ショパンコンクール、チャイコフスキーコンクールなど
名だたるコンクールで
入賞することが早道であるが。
世界の中では
幼少時から
その才能が世界の人々から認められ
コンクールをうけずに活躍する
ピアニストもわずかながらいる。
その中のひとりが
キーシンである。
30年以上前に
1回生の演奏を聴いたことが有り
その時の瑞々しい感性と
人並み外れたテクニックに
圧倒されたのを覚えていた。
そんなキーシンももう54歳になって
どんな演奏をするのか楽しみだった。
その演奏は・・・・
ベートーベンにはじまり
ショパン、ブラームス、最後はプロコフィエフと
意欲的なプログラムで有り
どの曲も的確なテクニックに裏打ちされた
圧倒的なスケール感であった。
キーシンは多くのCDもだしているので
演奏自体は予想はできたものの
それ以上にキーシンの成長に感動した。
それは
彼が紡ぎ出す
ピアニッシモの音、音楽に
やさしさ、悲哀など
僕の心を優しく包みこむような
温かい音色に感動したと共に
彼の人間的成長を感じ
彼なりの苦労を乗り越えて今があることを
感じたのです。
彼の素晴らしい演奏と共に
混乱のロシアを凜とした愛する気持ちが
演奏に感じられて
それがますます感動の嵐に誘っていった。
波
山本有三の小説「波」で
主人公が、
後からあとから押し寄せては砕けていく
波を前にして
次のように語っています。
「私たち親が散々苦しんだのだから
もはやこんなことを
こどもには経験して欲しくないと
思っていても、
こどもたちは
親が一生かけて経験したことを軽蔑して
打ち寄せる波のように
昔からほとんど変わることなく
同じ誤りを
くり返してしまう」
親になって
自分の気づいた過ちをしないように
育ても
こども達は同じ道を
歩んでるのかも知れない。
自分の親も
親と同じ苦労をしないように
育てられたはず。
でも、親としての苦労は
今も昔も変わらない。
人間が誕生してから
何万年も過ぎているけど
どんなに世の中が発達しても
人間は同じ苦労をしながら、経験して
生き続けている気がする。
打ち寄せる波のように
親の苦労は
いつの時代になっても
変わらない普遍の真理なのかも知れない。
川の流れのように
人生は
よく道そして川の流れにも
例えられます
美空ひばりの歌”川のながれのように”では
人ひとりの人生だけでなく
時代も、時の流れも
川の流れのようだと歌われています。
川の水は
穏やかに見えるときでも
流れています。
もちろん大雨が降ったあとには
周りのものを飲み込み
脅威になることもある
人生にも
いい時があるときと
悪い時もある
人生の激流に飲み込まれそうになることも
その清らかな流れにこころ癒やされることも
たびたびある。
そして
川の流れは永遠に続くわけではない。
最後は、母なる
生命の源の大海に
帰っていく。
海に帰った後も
水は蒸発し、雨となりまた川の水となり
また新たな人生が始まる。
輪廻転生のことを
僕たちに伝えているのかもしれません。
人生は
流れる川のようなものだとつくづく思うのです。
川の流れは止められないように
時の流れも止めがたく
昨日も、今日も、明日も
全く同じ時間というものはない。
そして
母なる源に帰っていき
そして次なる命を育み
そして
再びこの地の川に戻り
新たな経験の流れを経験する
人間の命は
そして人生は
本当に川の流れのようだと言える
いのち続く限り働きたい
自分が医者になった理由のひとつに
学生時代職業選択決める時
ずっと働きたい
いのち続く限り人のためになる職業に
つきたい
というのが頭にあった。
それは
自分が両親が遅くなって生まれた末っ子であり
僕が大学選択の時期になった時に
サラリーマンだった父が
勤め上げた会社を丁度退職する時期だった。
退職金をもらって
年金をもらって
悠々自適に暮らしていける時期だったけど
父には
まだ先がどうなるかわからない
自立させるまで
どれだけの時間とお金がかかるかわからない。
悠々自適な生活設計って
思いがけないので
それから、自分の足と手を使って働き続ける
職業を選択したのです。
毎日毎日
日銭を稼いで
僕を医者にしてくれました。
口には出さなくも
父の苦労は伝わるものでした。
だから
まだまだ元気で働けるのに
仕事を取り上げてしまう
当時の定年制を
こどもながらに恨めしく思ったのは事実です。
だから
僕は、死ぬまでというのは大袈裟だけど
自分の体力、気力が続く限り働ける
人のために働く決意をして
医者という職業を選択したのを覚えています。
時代は変わり
70、80になっても働くのが
普通になった時代になり
そんな時代の流れに乗って
今生きている、これからも生きていけることに
自分にこの道を教えてくれた
父に感謝しています。