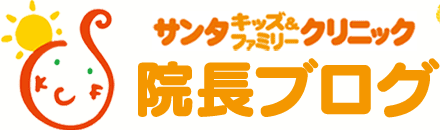検索
カレンダー
-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
リンク
「真実の医療」カテゴリーアーカイブ
安心して予防接種を受けられるために
この週末、予防接種のセミナーに出席しました。
最近予防接種が増えて
治療法のなかった病気を
防ぐことができるようになりました。
はしかは日本での根絶が宣言され
ポリオは世界的に根絶目前までになり
その他にも
27の病気が防げるようになりました。
予防のためのワクチンは
過去、現在を含めて最も成功した医療技術だといわれています。
これからの予防接種は
感染症だけでなく
アレルギー疾患、自己免疫疾患、癌治療
アルツハイマー病など
様々な分野の病気の予防そして治療薬として
益々発展していくでしょう。
でも、医療者の病気を防げるようになった
喜びとは反面
予防接種に抵抗感を持たれる方も増えています。
薬や注射などの治療をする場合
どんなにその治療が有効でも
安全じゃないとダメ。
患者さんは
有効で安全だとしても
安心できないと受け入られません。
それは、予防接種でもいっしょ。
予防接種は
よく効き、効果が永く保つように
医学的に安全なアシュバンドと呼ばれる物質を
混ぜています。
でもその物質が入ってることで
有効で安全な治療になっても
患者さんが不安に思うこともあります。
この物質が入っていないと・・・
例えば
インフルエンザワクチンでは
アシュバンド物質が入っていないので
効果が弱くなってしまい
インフルエンザにかかることもあるので
またまた、不安にさせてしまってます。
医学が科学が進歩したと言っても
誰もが安心できる完璧なものは
現時点ではありません。
今回学会に出席して
日夜研究、努力されて
誰もが安心できるワクチンが
実は開発されようとされてます。
まだまだ、安心なワクチンが完成するために
実用化されるには
時間はかかります
・・・といっても
その間も
病気にかかってしまう人がでてきてしまいます。
はしかも風しんもおたふくかぜも、インフルエンザも
予防接種のある病気は
実はとっても怖い病気。
合併症でいのちを落とすこともあります。
おたふくかぜ難聴のように、
一度合併症が起こると
治せない病気ばかりです。
みんながみんなではないけど
合併症、重症化して
いっぱい苦しんでる人たち、こども達を
僕ら小児科医はたくさん診てきました。
だから
病気にかかって欲しくない
苦しむ姿、重病になって
後悔してもらいたくないと思いを
いっぱい持って、願って
注射をしています。
不安があったら
その不安をそのままにしないで
僕たち小児科医に聞いてください。
少しでも不安が解消され
安心して受けられるようにお話ししますから。
予防接種の技術は
現代の車社会と一緒だと思います。
車はとっても便利。
歩くよりも早く目的に行くことができます。
でも、ひょっとして
事故にあって目的地に行けないかもしれません。
自動運転などの技術は進んでも
事故は無くなりません。
それでも
みんなは車を乗ることはやめません。
予防接種は
車よりもずっと安全だと思います。
予防接種のリスクを恐れるあまり
その大切ないのちが失われないよう
そして
みんなが安心して
健康で笑顔で暮らしていけるよう
僕たち医療者は努力していきます。
☆ 月曜日山陽小野田倫理法人会の設立式典に
お祝いに行ってきました。新しい単会設立うれしいですね。
本当におめでとうございます。
設立式典の懇親会では、新しい仲間が増えたことが嬉しくて、
料理も美味しくて、豪華なフルーツを目の前にして
一緒に行った防府市倫理法人会のメンバーと一緒に
かぶりついてしまいました。
こんな風に写真を一緒に撮れるメンバーが大好きです。
ありがとう
この週末は、台風の進路が気になりますね。
選挙もありますが、無理されずに事故のないよういい週末を。
カテゴリー: 真実の医療
安心して予防接種を受けられるために はコメントを受け付けていません
医学と量子力学
ナチュラルメディカルセンターで行ってる治療を
説明するためには
アインシュタインに触れないといけません。
アインシュタインは偉大な物理学者。
アインシュタインの提唱した量子力学は
今までの考え方を覆すものでした。
これまでの物理学とのちがいを
僕なりの言葉で言うと
これまでの物理学は
目に見えるものの法則性を見つける科学
量子力学は
目に見えないものの法則性を見つける科学
医学界は
これまでは、「人間機械説」という考え方のもと
人間の体は、機械のように部品でできている
だから、病気の時は
機械の部品を修理するように治せばいい。
そして、科学はどんどん進歩し
部品事態を取り替えるようになり
再生医療が花盛りになりました。
一方で
アインシュタインが提唱した量子力学の観点にたてば、
私たちは絶え間なく動き回る
分子、電子、素粒子で構成されています。
そして
肉体からそれを構成する最小単位の素粒子に至るまで
すべてのものがエネルギーを持っているのです。
言い換えれば、
人間の体も、すべてのものも
純粋なエネルギー体だということ
そして
自然治癒力をエネルギーとして
捉えられるようになったのです。
これまで、
エネルギーは目に見えなくても
感じていたと思います。
ヘトヘトに疲れると
病気に対する抵抗力が弱まることは
誰でも知っています。
エネルギーレベルが低下しすぎると、
筋肉から免疫系や心に至るまで、
あらゆる部分が緩慢になって、
ベットからでるのが
つらくなることもあったでしょう。
つまり、エネルギーは
あなたの基本的な生命力です。
プランクトンから人間まですべての生き物は、
エネルギーを持ってます。
病気の時にはエネルギーが低くなっています。
エネルギーを回復させることも
医療なんです
ナチュラルメディカルセンターでは
メタトロンとオステオパシーによって
そのエネルギーを調える治療を行っています。
☆今日午後は、クリニックはお休み。
午後の山口で収録が終わっての一枚
ホッとした瞬間、写真を撮られました。
いい時間を過ごせたことに感謝です。
カテゴリー: 真実の医療
医学と量子力学 はコメントを受け付けていません
目に見えないのは人間だけ?
目に見えないものって
見えているもの以上にあるのではないかと
思ったりします。
実は
人間だけが見えてないのかもしれないし
見えないものがあると思ってるだけかもしれない。
虫は、人とちがって複眼と言われる目を持っています。
魚も魚眼と言うし
鳥も大空から獲物を見つけられるめを持っていたり
蝶は、紫外線が見えるそうです。
ですから、モンシロチョウは
紫外線を吸収する雄のからだは黒く見えて
逆に雌のからだは反射して白く見えるらしいのです。
このちがいは人間には全くわからない。
つまり
人間が見えているものが
すべてではないということです。
見えてないと思ってるのは
ひょっとして
人間だけなのかもしれません。
だから
見えないからないのではなく
僕たちが見る力がないだけなのかもしれません。
見えないから
すべて否定する
見える世界だけにこだわる
科学の姿勢も
軌道修正する時を迎えているのかもしれません。
今見えているものって
本当は見えてないのかも
真実は見えてない部分にあるのかもしれませんね。
だから
僕は診療中も
目に見える人のからだを診るのはもちろんですが
めにみえなていないもの
心、魂からの訴え、サインを
見落とさないように
全神経集中して診療しています。
カテゴリー: 真実の医療
目に見えないのは人間だけ? はコメントを受け付けていません
かぜ
朝晩冷えていくと
咳、鼻水、熱と風邪ひきさんの受診が増えます。
誰でも知ってる風邪という病気。
でも、風邪というどんな病気なのがわかりにくいです。
今日は正しく風邪を理解していただけば
あわてなくていいかもです。
そこで、今日は風邪についてお話しします。
こどもはよく風邪をひきます。
年に5,6回はひくともいわれています。
よくある病名なので
くしゃみ、鼻水、のどの痛み、咳、熱、頭痛、だるい、食欲がない
などの症状があると
誰もが、あら、風邪ひいたかな?と思います。
でも
この症状って風邪に特有な症状ではありません。
なぜ、どうしてすぐ風邪と思ってしまうのでしょうか?
風邪の正式には
”風邪症候群”という病名です
症候群というのは
様々な原因で似た症状が泡われて、
大体同じような経過をたどる病気をまとめて
症候群と言います。
原因は様々でも、症状は同じ病気のことだと言えます。
風邪の原因の8~9割以上は
インフルエンザ、パラインフルエンザウイルス、RSウイルス、アデノウイルス
ライノウイルス、エコーウイルスなど代表的なものでもこんなにありますが
その他にも多数あり
原因となるウイルスは400種類以上もあると言われます。
ですから
風邪は何度もひくということになります。
残りの1割は
最近、マイコプラズマ、クラミジアなどが原因です。
赤ちゃんや保育園に行き始めたおこさんが
良く風邪をひいてしまうのは
これまでに、風邪のウイルスにさらされなかったこと
集団生活で
こども達自身が様々な風邪のウイルスを持ち込むことで
何度も、風邪をひいてしまうことになります。
風邪は、ほとんどがウイルスが原因なので
細菌に対する薬である抗生剤は
ウイルスには効きません。
ウイルスを直接やっつけることはできないので
咳、鼻汁、熱などの症状を和らげる治療が中心になります。
風邪の特効薬がないのは
こういう理由です。
こども達はすぐ風邪をもらってしまいます。
風邪のウイルスは
鼻、のど、気管支の粘膜で増えます。
そして、増えたウイルスが
くしゃみ、痰、咳、鼻汁にのって体の外に広がります。
抵抗力が落ちていると
感染した後に、またウイルスが増えて
症状を出してしまうことになるのです。
ですから
日頃から抵抗力をつけておくことが大事です。
特に冬は
気温が低く、乾燥しているので
風邪のウイルスは活発に活動し
身体が冷えると、呼吸器系の粘膜も血の巡りがわるくなり
抵抗力が落ちてしまいます。
日頃から
食事や水分を十分を摂ること
寒さに負けない体力作り
が大切になります。
またウイルスは
鼻水のついた指、ハンカチ、便などからうつるので
うがい、手洗いは
とても大切なことです。
風邪は
何度もひいて、強くなっていくもの。
風邪をひいたことに
一喜一憂せず
日頃からの体力作り、生活習慣が大切なのかもしれません。
カテゴリー: 真実の医療
かぜ はコメントを受け付けていません
よくなろうと頑張らなくていい
病気になって、治療が始まると
周りの人は
病気に負けるな
頑張れ・・・と応援し
病気の本人も
その気持ちに応え
病気を治すことを
闘病などといい
病気に負けないように
頑張る気持ちを自分自身で鼓舞します。
確かに
病気から治すために
周りの人の
自分を思う気持ち
悲しませてはいけない
まだまだ役割があると
自分の気持ちを鼓舞して
健康を目指せば
からだは患者さんの気持ちを受け取り
病気を治してくれるでしょう。
ただ単に
”よくなろう”と思うだけでは
決して
からだは健康に向かわないし
あまりいい結果は生まれないことを
傍で見ていて
感じることがあります。
これだけ頑張ってるのに
なぜ・・・と
治療するものとして
歯がゆくなることもあります。
でも
からだ(肉体)とこころがつながっている
人間の根本は
魂ではないかと
思うようになって
少しずつですが
そのちがいが見えてきたきがします。
ただ
「よくなろう」と思うことは
決して悪くない
力強いご自身の強いお気持ちだから
力になってくれるはずですけど
よくならない時、ひょっとして
「今、この状態は自分にとってよくない状態だと」
病気になった自分のことを
憎んではないでしょうか?
ここに至るまでの
ご自身の生き方を振り返ることなく
ただただ、病気を憎む。
それをバネに病気を戦う、闘病する力にするのですが
ここまでからだを苦しめたのは
からだではなく
ご自身ではないでしょうか?
それに気づいてもらいたいと
からだ自身は思っているのではないでしょうか?
もし
その点に気づくと
からだが気づいてくれてありがとうと
涙を流して!?喜んで
あなたの治りたい気持ちを
受け入れて
あなたのために頑張ってくれる
つまり
治癒に向かうはずです。
病気になったとき
ただ「よくなろう」と
闘う前に考えないといけないことがあった
病気の時も自分のからだに対して感謝することだと
僕も自分の病気をして
気がついたのでした。
カテゴリー: 真実の医療
よくなろうと頑張らなくていい はコメントを受け付けていません
熱がでるのも恵みです
患者さんの心配になる症状の一つに
「熱」があります。
熱があると
元気であっても
大変熱を下げないとと
解熱剤をつかったり
病院に夜中でも駆け込んでしまう
一番、心配な症状の一つでしょう。
熱→悪い病気→熱を下げないといけない
という構図ができあがっていると思います。
確かに
熱が出す病気は様々なあります。
重症な病気が隠れていることもあるので
注意を要する症状の一つであるのは
まちがいありません。
ですから
熱が出るとき
病院にかかることは間違いではありませんし
遠慮なく病院にかかって欲しいです。
でも、熱が出ている時に
心得ていて欲しいのは
熱→あわてて→熱を下げたい→解熱剤を使う
という行動パターンに走るのは
ちょっと待って下さい。
熱=病気のサイン だけれども
熱=悪いサイン とは限らないと言うことを
憶えていていただきたいです。
からだの中に
ウイルスや病原体がからだの中に入ると
様々な免疫細胞が働いて
からだを攻撃する病原体を排除しようとします。
その時、神経細胞は
免疫細胞が病原菌と闘っていることをキャッチして
免疫細胞を援護射撃するかのように
体温中枢神経に働きかけ
体温を上げて、熱を出させているのです。
病原体は熱に弱いからなのです。
熱が出ると言うことは
病気を治そうとする
からだの働きなんです。
そこで
あわてて、解熱剤を使ってしまうと・・・
からだがあわててしまいます。
あれれ、熱上げようとしてたのに
熱が上がらなかった。
大変だ、もっと全力で体温を上げないと
全力で熱をだそうとします。
その時
毛穴を塞ぎ、血管を縮ませ
体温が外部に漏れないような体制をとります。
だから、熱が上がるときは寒がったり、震えたりするんです。
そして
その時に熱を上げるために
体力も使って、ぐったりって言うことにもなります。
熱が出てるとき
ぐったりするのも心配だけど悪いことではなく
からだのサインでもあるんです。
からだが熱を出して集中して闘っているので
うろうろして体力消耗や神経集中できない状況に
させないためなんです。
からだが発する「寝とけ」のサインなんです。
からだが必死で闘ってるのに
そのからだからのサインを無視して
熱を下げ、体力を消耗する行動に走ると
後で、痛いしっぺ返しがくることもあります。
このように
「熱」ひとつとっても
自ら気づかないけれども
自分のためにからだが働いていることって
たくさんあります。
熱もからだからの大切なサイン
からだの中の神様が
守ってることを知らせてくれている
大切な恵なんです。
からだからのサインを発するのは
あなた自身のため。
あなたを苦しめるためではないんです。
病気になっても
あなたを守ってくれているからだに
感謝の気持ちを忘れずに
過ごさないといけないですね。
カテゴリー: 真実の医療
熱がでるのも恵みです はコメントを受け付けていません
脅威の免疫システムのおかげで今をいきられる
休日のある朝
たまたま観た
「驚異の免疫ネットワーク」という番組。
ちょっと難しいコロナウイルスと免疫のことを
鮮明な画像で解説している一般のかた対象の医学番組。
海外の放送局制作の番組のために
全編英語、でも字幕もあるので
映像の美しさにもひかれ
英語と医学の勉強もかねて最後まで見入ってしまった。
新型コロナウイルスという
新ウイルスと
体内の免疫力との戦いを解説していた。
免疫学の復習もかねて
書いてみると
体内にコロナウイルスであれ、インフルエンザであれ
ウイルスなどの未知の異物が体内に入ると
体内の食細胞が
未知の異物を発見しとらえ
食べてしまう。
その時に、そのウイルスなどの遺伝子を解析し
情報を他の食細胞を共有し
2回目以降の体内に侵入した際には
直ちに攻撃できるように準備している。
しかし
ウイルスも進化し
体細胞に発見されないように
忍者のように
体細胞の中に同化し偲びこんで
食細胞の発見から逃れようとする。
すると
食細胞は免疫第2段階として
侵入者の情報をB細胞という免疫細胞に
情報を渡す。
情報を受け取ったB細胞は
抗体を直ちに造り
細胞に異物が入り込む前に
捕まえようと
抗体を作り出して
ウイルスなどの侵入にあらかじめ備えていく。
この抗体を作る
免疫力を人為的に作らせるのが
ワクチンだということになります。
これで
もう、新型コロナウイルスが体内に
侵入しても大丈夫かと思いきや
新型ウイルスも進化し
どんどん強力かするのです。
今回の新型コロナウイルスでも
多くのかたがいのちを落とされました。
その人々の多くは
肺に血管が血液が詰まる塞栓症が
原因でなくなる方の死亡がほとんどでした。
そのなくなった方の
血管を調べてみると
血栓の中身は
血液とウイルスと食細胞そして食細胞のDNAだったのです。
つまり
免疫細胞の最後の姿だったのです。
イメージとして
食細胞が最後の力を振り絞って
自滅、自爆した
捨て身の戦法のなれの果ての姿だったのです。
これを医学的に
サイトカインストームだと言いますが
これを起こさせないようにしないと
いう考え方もあるけど
僕は
未知の予想外の相手の
コロナウイルスによって
身を呈して頑張って
捨て身の戦法までとって
闘ってくれる食細胞、免疫細胞に感謝です。
相手がどんなに強大でも
いつも僕のからだを守ってくれていることを
改めて感謝しかありません。
そこまでしてくれて
たとえ僕がなくなっても
責めることも、悔いることもありません。
でも、この免疫力も
急にできたわけではなく
人類が生まれたという5億年前から
様々な病原菌と闘ってきた病原菌との
長い長い歴史の結果なんです。
僕たちは
このご先祖さんから引き継いだ免疫力をもらって
現代社会を生きています。
こんな僕たちも
生まれたときは純粋で、免疫力は働いていません。
しかし
母乳をのみ
数々の感染症にかかりながらも
母の愛、両親の愛、ご先祖さんの力で
演繹力を育みながら
生きている、生き続けられていることを知り
生きていかなければならないということを
コロナウイルスが教えてくれていると思うのです。
カテゴリー: 真実の医療
脅威の免疫システムのおかげで今をいきられる はコメントを受け付けていません
気管支喘息発作
気管支喘息は慢性の病気、
治療をしないと発作を繰り返してしまう病気。
僕が医師になりたての時は
発作の時の治療が主でした。
特に小児喘息は、大きくなれば治る病気だと
言われていました。
でも
最近は
喘息の発作が起こってしまうと
気管支の状態が悪くなり
気管支喘息が治りにくなる。
そこで
気管支喘息の発作を起こさせない
気管支喘息で起こる
気管支の炎症を抑えることが重要な
ポイントになっています。
そのために
ステロイドの吸入、アレルギーの薬を飲んで
炎症を鎮めることになります。
でも、もし発作が起こってしまったら
発作を止めなくてはいけません。
そのためには
まずは、発作の程度を知ることが大切です。
発作の状態は大きく3つに分かれます。
①小発作とよばれる
軽くヒューヒューいうけど、元気に普通に生活できる
②中発作
ヒューヒュー、ゼーゼーが強くなって
話す時、辛かったり、食欲がなくなったり
少し呼吸困難な状態があります
③一番ひどい大発作
息苦しくて、動けない、横になれない
肩や身体全体を使って息をしている。
顔色が悪い
などの状態で治療が異なってきます。
発作の時の治療は
気管支を広げて、しっかり痰を切るために
吸入、内服薬、注射をします。
気管支喘息の発作で
一番困るのは、
気管支喘息の発作が夜間から朝方に起こることが多いこと。
ですから
昼間に咳が出ている時に
発作ではないか、病院で確認して
きちんと治療を受けておくことが
まず大事です。
そして、もし、夜中発作が出てしまった時は
水分をとって、痰が粘っこくならないようにする
衣服をゆるめる
発作の時は、あおむけに寝ると息苦しいので
布団やまくらを抱えて背中を丸めて横になると
楽になることがあります。
また、ゼーゼーしてても
眠れているようであれば
そのまま様子を見ていても大丈夫です。
ただ、
ゼーゼーしていて眠れない
息が早くなり胸がペコペコしている
顔色が悪ければ
夜中でも病院を受診しましょう。
喘息発作は
何もしないと必ず発作は起こします。
発作を起こすと
呼吸困難を起こし、とってもつらい病気。
ですから
発作を起こさないように
日頃から注意しておくことが
気管支喘息の発作で
あわてないための方法です
カテゴリー: 真実の医療
気管支喘息発作 はコメントを受け付けていません
遺伝子に組み込まれた生きる力
人類史上、
突然多くの方のいのちが
失ってしまう出来事がありました。…
古くはヴェスヴィオ火山の噴火で
ポンペイの町全体がのみこまれたり
日本でも、最近
東日本大震災などの自然災害で
多くのいのちが奪われてしまいました。
そして
中世ヨーロッパでは
ペストの大流行で総人口の1/4の方が亡くなり
20世紀では
スペイン風邪と呼ばれるインフルエンザの大流行で
6000万人の方が亡くなり
感染症が猛威をふるうこともあります。
でも
多くのいのちが奪われることって
病気や天変地異ばかりではありません。
先の第二次世界大戦のような戦争
原爆投下、テロ事件など
人間同士の欲望、争いによって
尊い多くのいのちが奪われています。
いのちが失われた悲しみは、
生き残った人も亡くなった方も
ずっとその悲しみが心にきざまれてしまいます。
だから、自殺も含め
全ての人のしあわせを奪う行為は
絶対にいけないことだと思います。
これらは歴史に残っている
不幸の歴史のひとつですが
有史以来、歴史に残っていないけど
最も多くの死の原因は
“こどもの死”です。
いつの時代も
多くのこども達が亡くなっていました。
病気になることもある
天変地異が起これば、かよわい命の炎は
たちまち消え去ってしまうことも多い。
“生まれてすぐ亡くなってしまう
“自然死“のこどもたちは
歴史には残ってないけど、とても多いのです。
だから、
赤ちゃんの体の中には
が生き残っていくための力が
備わっています。
口におっぱいが触れれば
必死で吸おうとする反射があります。
おっぱいを飲む時には
お母さんの目をじっと見つめます。
手に触れればに握ります。
笑いかければ、ニコってします。
低体温にならないように
赤ちゃんには熱を産生する
褐色細胞があります。
これらは
赤ちゃんが
生きて残っていくための
愛されるための
反射、仕組みです。
そして
この反射は、おとなににつれて
なくなってくるんです。
でも、
反射、仕組みは消えても
その生きていく術は
遺伝子の中にちゃんと残って
次の世代の赤ちゃんに
引き継がれて生きます。
僕たちの体の中には
生きていくための力が
神様からもらい
先祖代々から受け継いがれ
生きていく力が備わっているです。
その素晴らしい生きる力を大事にして
いのちを大切にして
生きていくことが
健康であることに
つながるのだと思います。
カテゴリー: 真実の医療
遺伝子に組み込まれた生きる力 はコメントを受け付けていません
薬より大切なこと
人は
病気になった時はもちろんだけど
病気を予防するために考えた時
薬やたべもののことをまず気にします。
日常の診療でも
みんな薬を求めて受診される
だから
薬が飲まなくていいよと言うと
喜んでもらえるかと思うけど
実際は不服そうな顔をされる方が多い。
僕は
病気を治すためには
薬だけではなく
薬よりもっと大切なことがあります
プラシーボ効果という言葉が
医学会にはあります。
それは、たとえ偽薬であっても
服薬される患者さんが
本物の薬であると信じて服薬すれば
実際効果があるというが経験されているのです。
同じ薬を飲むにしても
仕方なく渋々飲むのと
「これはすごくよく効く」と
前向きな気持ちで服薬するかでは
治療効果に大きな差が出るのです。
このプラシーボ効果は
人間のからだが持っている
自然治癒力の働きで説明することができます。
いい薬だ、この薬を飲めば絶対治るなど
より強いイメージや信念を持って服薬すると
免疫の中枢器官である間脳が刺激され
間脳の働きが活発になリます。
その刺激が神経系に情報伝達されると
血液中のリンパ球が強化され
病気に対する免疫力が高まって
従って
自然治癒力も高まると言うわけなんです。
人間には
生まれたときから
元々備わっている自然治癒力があります。
その生まれつき持っている
自然治癒力のパワーは
自身が考えているより
はるかに強力で
どんな難病でも治すだけの力があるとも
言われています。
その底知れない
自然治癒力をひきだせるのも
自分自身しかないのです。
治りたい、なおるなど
その病気に打ち勝つんだという
強い気持ち、信念をもち
心の底から
自身のもつ自然治癒力を信じることでしょう。
僕も入院したとき
絶対治る、これまで通りの仕事、生活をすると
と思ってましたし
それが現実になったのは
薬ではありません。
自分自身の力
すなわち
自然治癒力のたまものなのです。
この世には
プラシーボ効果が存在します
つまり
自身のもつ思いやイメージが強ければ
奇跡を起こす力が
誰にも備わっているのです。
カテゴリー: 真実の医療
薬より大切なこと はコメントを受け付けていません